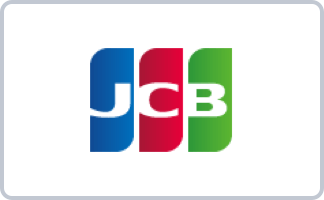声の地層 災禍と痛みを語ること|瀬尾 夏美
¥2,310 税込
残り1点
別途送料がかかります。送料を確認する
生きのびるブックス 2023年
ソフトカバー 288ページ
四六判 縦188mm 横128mm 厚さ16mm
- 内容紹介 -
多くを失い身一つになっても、集えば人は語りだす。
伝える人と、耳をすます人の間に生まれた、語り継ぎの「記録文学」。
「すこしの勇気を持って、この人に語ってみよう、と思う。その瞬間、ちいさく、激しい摩擦が起きる。マッチが擦れるみたいにして火花が散る。そこで灯った火が、語られた言葉の傍らにあるはずの、語られないこと、語り得ないことたちを照らしてくれる気がして。それらを無理やり明るみに出そうとは思わない。ただその存在を忘れずにいたい」(はじめに)
- 目次 -
はじめに――語らいの場へようこそ
第1章 おばあさんと旅人と死んだ人
第2章 霧が出れば語れる
第3章 今日という日には
第4章 ぬるま湯から息つぎ
第5章 名のない花を呼ぶ
第6章 送りの岸にて
第7章 斧の手太郎
第8章 平らな石を抱く
第9章 やまのおおじゃくぬけ
第10章 特別な日
第11章 ハルくんと散歩
第12章 しまわれた戦争
第13章 ハコベラ同盟
第14章 あたらしい地面
第15章 九〇年のバトン
声と歩く――あとがきにかえて
- 前書きなど -
はじめに―語らいの場へようこそ
災禍に遭う。困難を抱える。大切なものを失う、奪われる。できるならそんなことは誰の身にも降りかからない方がよいのだけれど、現状、なかなかそうもいかない。自然災害に見舞われたり、事件や事故に巻き込まれたり、生活圏で戦争や紛争が始まったり、あるいは心身に傷を抱えることもあるし、生きづらさに深く悩むことだってある。この地球上に生きている限り、まさにいま、見知らぬ誰かが、自分自身やとても近しい人が、苦しい経験をするかもしれない。その予感自体が恐怖であるから、日常生活を送るうえではあまり想像したくはない、忘れていたいものではある。だけど、だとしても、逃げているばかりでよいのだろうか? とも思う。
もちろん防災的な観点を用いて、リスクから逃げずに向き合い、できるだけ未然に対処すべし! といった答えを導くことはできるかもしれないけれど、わたしにはもうひとつ意識していたいことがある。それは、先立って災禍を経験した人びとの存在である。彼らの多くが、未来に生きる人びと―ほかでもないわたしたちの苦しみがすこしでも和らぐようにと願って、体験と記憶をふりかえり、検証し、言葉にし、それらを記録に残したり、語り継ぎを試みたり、あるいは物語を編み上げたりしてきた。さらに、彼らの傍らにはその声を受け止めてきた人がいて、またその人から話を聞いた人がいて……だからこそ、災禍の語りや記録は、いまわたしたちの目の前に存在している。そんなちいさなバトンを手渡すような連綿とした営みを想像すると、その凄みと愛らしさに圧倒される。ならばせめて、その声を聞く努力をしてみたい。
こんなことを考えるようになったのは、この一〇年あまり、言い換えると、二〇一一年に発生した東日本大震災以降、自身の経験を言葉にして伝えようとする人びと、あるいは他者の経験を語り継ごうとする人びとにたくさん出会い、話を聞かせてもらってきたからだ。語り手にとっても聞き手にとってもしんどいことをなぜわざわざ? と問われることもあるけれど、災禍を語らう場に招かれ、その豊かさを知ってしまうと、なかなか離れがたい。語ることはときに酷く苦しい。聞くことだってそうかもしれない。だけど、語らいの場がもたらすものはそれだけではない、と信じている。たくさんのものを失い、身ひとつになっても、集えば人は語り出す。ちいさな輪のなかでともに泣き、怒り、許しあったり笑いあったりする。話す人、聞く人、沈黙する人、相槌を打つ人。語りは居場所をつくる。その実感が大きい。
はじまりは発災から間もない頃、ボランティアで訪ねた避難所や泥だらけの家々での出来事だった。わたしは当時大学を卒業したところで、やれることがあればなんでもすると意気込んで、友人とふたりで “被災地”に向かった。しかし情けないことに、到着したその現場で、自分が力持ちでも器用でもなく、あまり役に立たないことに気がつく。それで所在なげにしていると、“被災者”たちが次々と声をかけてくれた。あんだ、わざわざ遠くから来てくれたの! そう言ってまじまじとこちらを見つめて、旅の者にはせめて土産のひとつでも持たせなければ、という面持ちで訥々と語り始める。
日常の想像力では追いつかない、巨大な力で捻じ曲げられた風景をともに見つめながら、凄絶な“あの日”とそれからのこと、失われたものたちのことを聞く。ただ、思いがけずその場はやわらかかった。被災して間もない語り手と、どこかから迷い込んできた旅の者が会話をする。それぞれの立場の違いを考えればピリピリと緊張が走るけれど、会話を進めていくとそれは徐々に解け、場に集うひとりひとりとして付き合う形となる。
その人が語り、わたしは聞く。その人がわたしの様子を見ながら、次の言葉を選んでくれているのがわかる。恐れ多い。ここに居るのがわたしでいいのだろうか、と思う。だけど、たとえほんの一部だとしても、その人の大切な経験を手渡そうとしてくれることが嬉しい。だから、できるだけはっきりとうなずく。すべてはわからなくても、聞いています。聞きたいです、と伝えたくて。そうして続いたしばしの会話を締めくくるとき、その人は言った。いま話したことを、きっと誰かに伝えてくださいね。大変なことになった、とわたしは気がつく。再会を誓って別れる。
いまわたしが居るのは、今後確実に歴史に刻まれるであろう巨大災害の“被災地”である。そこで話を聞かせてくれた人びとのほとんどが、誰かに伝えてね、と言っていた。話を聞いた者には、語り継ぎの役目が託される? なんてこった。軽くうろたえながら、とはいえどうすればいいのだろう、と具体的なことを想像してみる。そもそもわたしがやっていいことなのだろうか。相手がどれくらい本気なのかもわからないけれど、せっかく聞かせてもらったことは、誰かに伝えてみたい、と思った。
語り継ぎとは、こんなにちいさな現場の積み重ねによるものなのか。それは出来事のすぐあと、身ひとつで肩を寄せ合うその瞬間から始まっている。そのことに新鮮に驚き、突き動かされるように旅を始めてから、一〇年以上が経つ。
この本は、二〇二一年の一月から二〇二二年春までの一年半にわたり、『声の地層 〈語れなさ〉をめぐる物語』と題して続けた連載と、三本の書き下ろしで構成されている。
被災地域を歩いて話を聞かせてもらった日々の中で、自分の関心は“語れなさ”にあると感じるようになった。それは、場に集う人びと、聞き手と語り手、人間同士のあいだに発生するものだ。そもそも語りとは、語り手が一方的に自分の感情や考えをぶつけるものではなく、目の前にいる聞き手とのやりとりによって編まれるものだと思う。途中でその役割が交代することだってあるし、それぞれが自分の内に思わぬ言葉を見つけたり、ともにあたらしい物語を発見したりする楽しみがある。
ただ、どんなに信頼する相手との穏やかな場であったとしても、“語れなさ”は発生する。たとえば、語ることで相手を傷つけたり、関係性が崩れたりすることが怖くなる。自分や誰かの大切な体験や記憶が、誤解されたり損なわれたりするのは避けたい。わたしたちは自分の内側でさまざまなことを考え、逡巡し、迷いながら言葉を選び、声に出す。こうして〝語れなさ〟は語りを抑圧し、制御することがある、といえるかもしれない。あるいは、だからこそコミュニケーションが円滑になるのだ、と開き直ることもできるかもしれない。
たしかに、“語れなさ”がどう働くのかを検証することも興味深いとは思うけれど、わたしが気になっているのは、言葉を声に出す前の一瞬のひっかかり、そのもののことだ。置かれた境遇も考え方も異なる人たちが、互いのすべてを分かり合うことは難しいと感じながらも、それでも関わろうとする。すこしの勇気を持って、この人に語ってみよう、と思う。その瞬間、ちいさく、激しい摩擦が起きる。マッチが擦れるみたいにして火花が散る。そこで灯った火が、語られた言葉の傍らにあるはずの、語られないこと、語り得ないことたちを照らしてくれる気がして。それらを無理やり明るみに出そうとは思わない。ただその存在を忘れずにいたい。
連載を開始した二〇二一年は東日本大震災から一〇年目の年だったが、新型コロナウイルス感染症の拡大という世界的、長期的な災禍の始まりとも重なった。また、気候変動の影響もあって世界各地で自然災害が増加し、二〇二二年二月にはロシアによるウクライナ侵攻が始まった。予想もしなかった災禍が重なり、社会は大きく揺らいでいる、と思う。経済難は深刻化し、格差が広がり、とくにインターネット空間には差別的な言葉と行為が溢れている。ふつうの日常に分厚い不安感が広がっていくのを感じながら、わたしはより切実に、語りを聞きたい、語らいの場が必要だ、と思うようになった。
そうして、かつて戦争や自然災害などの災禍を経験した人びとに会いに行くと、彼らが自身の過去を反芻しながら、いままさに苦しい境遇にある人びとに気持ちを寄せていたことが印象に残っている。また、わたし自身は、こうして災禍の語りを聞き歩く中で、自分や身近な人の日常にある痛みについて、ほんのすこしずつ、向き合えるようになってきた。災禍は非日常的なものだけれど、その渦中にもその後にも日常はある。そんな実感を込めて災禍を語る人びとに、ごく身近にある“語れなさ”に触れるための手つきを教えてもらった。
この本は奇しくも、こうして大きく揺れていた(いや、これからもっと困難な時代が訪れるのでは、という不安が強いのだけれど)社会のちいさな記録にもなったと思う。ひとつひとつの章は、「物語」と「あとがたり」で構成している。何かを語ってくれたその人が感じていたであろう〝語れなさ〟と、その語りの傍らにあったはずの、語られないこと、語り得ないことを忘れずに残しておくために、創作の「物語」という余白を含み込める形を選んだ。「あとがたり」には、おもに実際の語りの場の様子やそのときどきの気づきを記している。
身を寄せ合い、輪をつくり、語らう。そこで、自分たちに起きたこと、起きていることを確かめ、互いの知恵を交換しながら、これからについて話しあう。誰もがきっと必要としているちいさな場の連なりが、そっと灯された物語を、遠くまで運んでゆくのを想像しながら。
誰もがその輪の中に招かれることを祈って。
- 著者プロフィール -
瀬尾夏美 (セオ ナツミ) (著)
1988 年、東京都生まれ。土地の人びとの言葉と風景の記録を考えながら、絵や文章をつくっている。2011年、東日本大震災のボランティア活動を契機に、映像作家の小森はるかとのユニットで制作を開始。2012 年から3 年間、岩手県陸前高田市で暮らしながら、対話の場づくりや作品制作を行なう。2015年、宮城県仙台市で、土地との協働を通した記録活動をするコレクティブ「NOOK」を立ち上げる。現在は、東京都江東区を拠点に、災禍の記録をリサーチし、それらを活用した表現を模索するプロジェクト「カロクリサイクル」を進めながら、“語れなさ” をテーマに旅をし、物語を書いている。著書に『あわいゆくころ―陸前高田、震災後を生きる』(晶文社)、『二重のまち/交代地のうた』(書肆侃侃房)、『10年目の手記―震災体験を書く、よむ、編みなおす』(共著、生きのびるブックス)、『New Habitations:from North to East 11 years after 3.11』( 共著、YYY PRESS)がある。
-
レビュー
(105)
-
送料・配送方法について
-
お支払い方法について
¥2,310 税込