-

植物のすごい繁殖戦略 花のしくみはこんなに違う! | 保谷 彰彦
¥2,090
河出書房新社 2025年 ソフトカバー 224ページ 四六判 - 内容紹介 - 花を咲かせない? 受粉しない? 種子をつくらない? 驚きと不思議に満ちた植物の生殖について、さまざまな植物を例に取り上げながら余すことなく紹介する、植物の奥深さを楽しめる一冊。 ・ 植物はこうして命をつないでいる! ・ 虫が来ないときに備える あえて咲かない 受粉しない 虫と風どっちも味方にする ・ 身近に生えている植物なのに驚きと発見の連続! 知られざる受粉のしくみと見事なまでの繁殖戦略! ・ ・ ■もくじ 【1】花の旅のはじまりに いろいろな花/花の誕生/花のつくりの基本/花が咲くのは何のため?/受粉から受精に至るプロセス/送粉のしくみ/送粉者/送粉者を誘い寄せる花/自家受粉と他家受粉/送粉シンドローム ・ 【2】ほかの花と結ばれるしくみ 自他を見分ける/タイミングをずらして交わらない/ 離れていれば交わらない/異なるタイプとつながる/ 花の左右が違う/究極の戦略は広がらない ・ 【3】虫いらずのしくみ 目立たなくていい/咲かずに実を結ぶ/来るものは拒まず、来なくても構わず/イネを知る/じつは二刀流も多い ・ 【4】クローンで殖えるしくみ クローンの種子で殖える/体の一部で殖える ・ 【5】花蜜をめぐるしくみ ただ甘いだけじゃない/花は送粉者だけのものではない/花蜜のありかへ導く/穴をあけて盗む/花蜜に毒を混ぜる ・ 【6】花蜜以外で誘うしくみ 胸部の筋肉がふるえる/植物だって熱をだす/子房を食べてもらう見返りに/あるある詐欺もいろいろ/大きくてよいこともある ・ 【7】まだある、見なれた花のしくみ 調和のとれた集まりで繁栄する/色の変化で知らせる/原始的ではない/この二刀流は古くて新しい - 著者プロフィール - 保谷 彰彦 (ホヤ アキヒコ) (著) 国立科学博物館植物研究部などを経たのち、「たんぽぽ工房」を立ち上げ、サイエンスライターに。著書に『タンポポハンドブック』(文一総合出版)、『ヤバすぎ!!!有毒植物・危険植物図鑑』(あかね書房)など。
-

どうぶつのないしょ話 | 佐々木 洋
¥1,980
雷鳥社 2025年 ソフトカバー 224ページ 四六変形判 縦128mm 横168mm 厚さ17mm - 内容紹介 - じつはナマケモノは泳ぎが得意? シロクマの毛は白じゃなくて透明? ダンゴムシは“昆虫”ではなく“エビのなかま”だった!?“知っているつもりだった”思いこみがくつがえる、どうぶつたちの「ほんとうの話」を、写真つきで50個ご紹介します。登場するのは、動物園で人気のライオン、パンダ、ハシビロコウなどのどうぶつから、道ばたで出会える身近ないきものまで。見た目、行動、生き方に隠れたひみつを、こっそりと楽しくひもといていきます。ページをめくるたびに「へぇ~」「そうだったの?」と、意外な発見の連続! 動物園へのおでかけや、お散歩がもっとおもしろくなるはずです。著者は、『ダーウィンが来た!』(NHK)や『スーパーJチャンネル』(テレビ朝日)などで活躍するプロの自然解説者、佐々木洋さん。 経験豊富な自然の知識と、ユーモアのある語り口で、動物の世界の奥深さを伝えます。 - 目次 - 1章 どうぶつえん編 見たままが、ほんとうとはかぎらない…【姿かたちのひみつ】 ・シロクマの毛は白ではなく透明 ・キリンのツノは2本ではなく3本 ・パンダのしっぽは黒ではなく白 ・ラクダのこぶの中身は水ではなく脂肪 ・フクロウにも耳のあるものがいて、ミミズクにも耳のないものがいる ・ものすごく小さなゾウの仲間がいる ・ニホンザルにおでこはほぼない ・コアラにしっぽはない ・シロサイもクロサイも灰色 ・シマウマは縦縞ではなく横縞 ・カモシカはシカではなくウシ コラム 動物園の「訪問者」にもご注目! 2章 どうぶつえん編 そのしぐさには、ちゃんとわけがある…【行動のひみつ】 ・ゴリラは「グー」ではなく「パー」で胸を叩く ・カンガルーのお母さんの袋から顔をだすのは赤ちゃんではなく"幼児" ・狩りをするライオンはオスではなくメス ・レッサーパンダが2本足で立つのは芸ではなく習性 ・ヘビクイワシはクモも食べる ・ゾウは耳だけではなく足の裏でも音をキャッチする ・水に入るのが好きなネコがいる ・動物園のハシビロコウはけっこう動く ・死んだふりをしてもクマに喰われる ・イノシシは急に曲がれる コラム セミの羽化は夜の動物園で 3章 どうぶつえん編 じつはこんな性格だった…【生き方のひみつ】 ・チンパンジーは猛獣 ・ウサギは寂しくても死なない ・バクは夢ではなくリンゴを食べる ・ナマケモノもやるときはやる ・タヌキ汁の中身はタヌキではなくほぼアナグマ ・サルはサルスベリですべらない ・マツの木にとまるのはツルではなくコウノトリ ・カバはおとなしくはなく超危険生物 ・ほとんどの動物は冬眠しない コラム 動物「感」察のススメ 4章 身近ないきもの編 名前や見た目にまどわされて…【姿かたちのひみつ】 ・コイのひげは2本ではなく4本 ・カタツムリの中身をだしてもナメクジにならない ・アオダイショウは青ではなく緑 ・カブトムシは「ツノ」、クワガタは「アゴ」 ・タヌキの両目のまわりの黒い色は、つながっていない ・モンシロチョウの紋の色は白ではなく黒 ・ダンゴムシは昆虫ではなくエビやカニの仲間 ・ウメにウグイスではなくメジロ ・点があるからというより、お天道様へ向かうのでテントウムシ ・カルガモは軽くなく重い ・雨のときによくいるからではなく、飴のにおいがするからアメンボ コラム 「チョウの保育園」を作ろう 5章 身近ないきもの編 すぐそばのふしぎに気づくとき…【行動のひみつ】 ・カメはのろくなく、けっこう速い ・モグラは太陽を浴びても死なない ・コウモリは目からではなく口や鼻から超音波をだす ・チョウもガも、翅を開いてとまることも閉じてとまることもある ・トンビはタカを産む ・セミは1週間ではなく1か月ぐらい生きる ・オシドリは毎年結婚相手を変える ・ドングリに開いた穴は虫が「入ったあと」ではなく「でたあと」 ・トンボは後ろにも下がれる コラム「だるまさんがころんだ」鳥 - 前書きなど - ぼくはこれまで40年以上にわたり、子どもからお年寄りまで、幅広い年代の人たちに自然の魅力を伝え続けています。その中で、国内・国外問わず、数えきれないほどさまざまな土地を訪れました。それは、自然を愛する人を増やすことで、自然をみんなで大切にしていきたいからです。 小さなダンゴムシから大きなゾウまで、観察の対象はほんとうにさまざまですが、それらについて日々解説をしているうちに、多くの人々がちょっとした誤解や思い込みを持っていることに気がつきました。たとえば、「ゴリラはジャンケンのグーの手で胸を叩く」、「翅を開いてとまるのはガ、それをとじてとまるのはチョウ」……。そんなふうに、なぜか信じてしまっている"決まりごと"のような話、みなさんにもきっと思い当たることがあるのではないでしょうか。この本では、そんな思い込みがふわりとくつがえるような、動物たちの「ほんとうの話」をこっそりお届けします。 - 版元から一言 - いま、日本各地の動物園から少しずつ動物が減りつつあります。話題になったように、ジャイアントパンダが中国へ返還されることが決まり、ニュースでも大きく取り上げられました。それに伴い、「動物園に行こう」というきっかけそのものが減ってしまっているのかもしれません。けれど、動物園は本来、普段なかなか出会えない動物たちと出会える、とても貴重な場所です。特に子どもにとっては、実際に動物を目にする体験そのものが、心を動かし、世界を広げてくれるかけがえのないもの。だからこそ、動物たちの姿が少しずつ見られなくなる今、この本を通じて、「動物園に行ってみよう!」という気持ちを届けられたらと思いました。 本書では、パンダやゾウ、シマウマといったおなじみの動物たちにまつわる“意外なほんとう”を、ユーモアあふれる解説で写真とともに紹介しています。動物園で人気のある動物たちだけでなく、街の近くにいる生き物たちも掲載しています。動物や身近な生き物を実際に自分の目で見て、「こんな生き方をしていたんだ!」と感じることで、子どもも大人も、自然の面白さに改めて気づくことができるはずです。 この本が、動物に興味を持つきっかけになり、動物園や身近にある自然に足を運ぶひとつの手がかりになれば――そんな思いを込めて制作しました。 - 著者プロフィール - 佐々木 洋 (ササキ ヒロシ) (著) プロ・ナチュラリスト(プロフェッショナルの自然解説者)。東京都出身、在住。国内外で、「ささき隊長」として40年以上毎日のように自然のすばらしさを伝え続けている。主な出演番組に『ダーウィンが来た!』(NHKテレビ)、『スーパーJチャンネル』(テレビ朝日)、『ラジオ深夜便』(NHKラジオ)など。主な著書に『生きものハイウェイ』(雷鳥社)、『きみのすむまちではっけん!となりの「ミステリー生物」ずかん』(時事通信社)、『みんなのまわりの気になる生きもの』(技術評論社)などがある。
-

英国王立園芸協会とたのしむ 植物のふしぎ | ガイ・バーター(著), 北 綾子(訳)
¥2,970
河出書房新社 2025年 ハードカバー 224ページ A5判 縦218mm 横149mm 厚さ24mm - 内容紹介 - タネはなぜ、自分の進むべき道をまちがえないの? 竹は花? ミミズは地中で何してる?……世界屈指の園芸アドバイザーが驚くべき植物の姿を130のQ&Aで答える。美しくギフトにも最適。 - 著者プロフィール - ガイ・バーター (バーター,ガイ) (著) 1804年創立の英国王立園芸協会園芸チーフアドバイザー。何千人もの園芸家へアドバイスを行う RHS会員諮問として活躍、絶大な信頼を集める。自身も庭師で、四季を通して果物や野菜の栽培を楽しんでいる。 北 綾子 (キタ アヤコ) (訳) 日本女子大学大学院修了。訳書に『鎖された声』『ブラッド・クルーズ』、ロンドンの小悪党シリーズ 『キットとパーシー』『ロブとマリアン』
-

アリ先生、おしゃべりなアリの世界をのぞく | 村上 貴弘
¥1,650
扶桑社 2025年 ソフトカバー 240ページ 四六判 - 内容紹介 - アリの生態に魅せられた、“アリ先生”の研究の日々! ・7歳から「いきものがかり」 ・ランニング通勤中にエサ集め ・10時間ぶっ通しで観察(トイレは2分) ・アリ語で寝言を言う などなど、ユニークすぎるエピソードが満載。 知的好奇心を満たす、子どもから大人まで楽しめる科学エッセイです。 巻末には先生のイラストによるアリ図鑑も収録。 アリのおしゃべりが聞ける<特典音声>つき! ※本書は、扶桑社新書『アリ語で寝言を言いました』『働かないアリ 過労死するアリ~ヒト社会が幸せになるヒント』を再構成し、 大幅に加筆修正したものです。 【目次】 はじめに 地球はアリの惑星 Episode1 昆虫少年時代 いつも生き物がそばにいた/鳴いたオンドリと飛んだチャボ/昆虫図鑑に椋鳩十、そしてファーブル/昆虫少年がアクティビストに/「サラリーマンにはなれない」 Episode2 ムツゴロウさんが教えてくれたこと 人生不安に陥った小学生時代/ムツゴロウさんから受けた影響/夢の変遷とたどり着いた大学研究室/オオアリとムネボソアリを間違える/アリってすごくない!? Episode3 ハキリアリの高度な社会 楽園、バロ・コロラド島へ/キノコアリとの運命の出会い/複雑で洗練されたハキリアリの社会/ハキリアリと農業/ハキリアリと祖先的なキノコアリの違い/2:6:2の法則 Episode4 アリ研究者の日々 ランニング通勤と葉っぱ採り/ハキリアリを個人輸入/ハキリアリの飼育/ギアナ高地で職務質問/難しくなった海外調査 Episode5 フィールドワークの物語 フィールドワークの「7つ道具」/腕と脚には「ダニホイホイ」/熱帯雨林でヒンズースクワット/ハキリアリの巣掘り/ハキリアリの巣が滅びるとき Episode6 最終日には気をつけろ! 素の「昆虫好き」に戻るとき/ハキリアリのゴミ捨て場/グンタイアリの中心で/キジムナーのイタズラ/野宿したベンチで足に……/フィールドワークは臆病に Episode7 地味で楽しい行動観察 「ゾーン」に入る/アリの体に印をつける/基本、「楽しい」行動観察/デビュー作で小さな大発見/行動観察の最新事情/じつはスゴいアナログ手法 Episode8 遺伝解析への挑戦 動かない「カドフシアリ」/カドフシアリの脳を解剖する/世界に先駆けた「遺伝解析」/DNA解析法の黎明期/不便だけれどチャンスがあった Episode9 アリは何をしゃべっているのか アリはしゃべる/アリの化学コミュニケーション/きっかけとなった「ある論文」/初めてハキリアリの声を聞いた夜/動物は会話をしているのか?/小型高性能録音装置、2万円也/キノコアリ5種500分の声を録音/難しいプレイバック実験/キュキュキュ、キョ、ギギギ/女王アリの一言/アリは何をしゃべってる? Episode10 アリとコミュニケーションと進化 アリのおしゃべりを求めて/音のコミュニケーションとアリの社会進化/コミュニケーションが必要な仕事/無口なオスアリ/アリの「口」と「耳」/フェロモンより音/アリと腹を割って話してみたい Episode11 人間がアリ社会から学べること 寝ないアリの寿命は短い/不眠不休で育児をするアリ/アリは果たして勤勉か?/「パラサイト夫婦」の生涯/フリーライダー、許せませんか? アリ図鑑 ヨコヅナアリ/ナベブタアリ/ミツツボアリ/ハキリアリ/グンタイアリ/アギトアリ/ウロコアリ/サムライアリ/パラポネラ/ヒアリ/トゲアリ/ウミトゲアリ/サハラギンアリ/アカツキアリ/カクレウロコアリ/骸骨を集めるアリ/ヤドリウメマツアリ/ヤマトムカシアリ/クロヤマアリ/イエヒメアリ おわりに ずっと「見ていたい」 - 著者プロフィール - 村上貴弘 (ミラカミタカヒロ) (著) 岡山理科大学理学部動物学科 教授 1971年、神奈川県生まれ。茨城大学理学部卒、北海道大学大学院地球環境科学研究科博士課程修了。博士(地球環境科学)。研究テーマは菌食アリの行動生態、社会性生物の社会進化など。NHK Eテレ『又吉直樹のヘウレーカ! 』ほかヒアリの生態についてなどメディア出演も多い。著書に『働かないアリ 過労死するアリ』『アリ語で寝言を言いました』(ともに扶桑社新書)、共著『アリの社会 小さな虫の大きな知恵』(東海大学出版部)など。
-

しぜんの ふしぎ! かがくの わ! ぜつめつした いきもの | 今泉忠明(監修), 川崎悟司(絵)
¥1,650
フレーベル館 2025年 ハードカバー 28ページ 縦270mm 横210mm 厚さ9mm - 内容紹介 - なぜ?と思ったときが学びのスタート! 子どもたちの好奇心の種をまき、考える力を育む、かがく絵本シリーズ。 『ぜつめつした いきもの』では、恐竜などの今は会えない個性豊かな絶滅生物を紹介。そして、今まさに絶滅の危機にある生き物たちのために、これから私たちになにができるのかを考えていきます。 初出「しぜん-キンダーブック」2024年3月号。 - 著者プロフィール - 今泉忠明 (イマイズミタダアキ) (監修) 1944年東京都生まれ。動物学者。文部省(現・文部科学省)の国際生物学事業計画調査、日本列島総合調査、環境省のイリオモテヤマネコ生態調査などに参加。ねこの博物館館長、日本動物科学研究所所長などを歴任。動物の魅力をフィールドワークや、書籍の執筆や監修などを通して幅広く伝えている。 著書に『誰も知らない動物の見かた 動物行動学入門』(ナツメ社)、『気がつけば動物学者三代』(講談社)など多数、監修書に「ざんねんないきもの事典」シリーズ(高橋書店)、「わけあって絶滅しました。」シリーズ(ダイヤモンド社)など多数。 川崎悟司 (カワサキサトシ) (絵) 1973年大阪府生まれ。イラストレーター。恐竜や古生物をはじめ、様々な生き物のイラストを描き、研究。趣味のイラストを収録したウェブサイト「古世界の住人」を運営し、古生物に関する解説なども行なっている。 著書やイラストに『カメの甲羅はあばら骨』(SBクリエイティブ)、『絶滅したふしぎな巨大生物』(PHP研究所)、『キモイけど実はイイヤツなんです。』(KADOKAWA)、『恐竜大決戦』(実業之日本社)など多数。
-

虫を描く女(ひと) 「昆虫学の先駆」マリア・メーリアンの生涯 | 中野 京子
¥1,320
NHK出版 2025年 NHK出版新書 ソフトカバー 256ページ 新書判 - 内容紹介 その画家はなぜ、強烈に「知」を求めたのか──? 近代の夜明け前、フンボルトやリンネ、ダーウィンよりはるか昔に、昆虫学という学問が存在しないなか独学で研究を行い、メタモルフォーゼ(変態)の概念を絵によって表現、さらに大西洋を渡って南米を調査旅行し、昆虫や植物の姿を生き生きと描写した破格の女性が17 世紀にいた。小さな虫の中に「神」を見たその女性、マリア・シビラ・メーリアンとは何者だったのか──。科学と芸術が混じり合った豊かな時代の輝かしい偉業を、中野京子が生き生きと蘇らせる。2002 年刊の幻の名著、『情熱の女流「昆虫画家」──メーリアン波乱万丈の生涯』が満を持して復刊! 第一章 フランクフルト時代(~18歳)──小さき虫に神が宿る 第二章 ニュルンベルク時代(~38歳)──科学と芸術の幸福な融合 第三章 オランダ時代(~51歳)──繭の中で変化は起こる 第四章 スリナム時代(~54歳)──悦びの出帆 第五章 アムステルダムでの晩年(~69歳)──不屈の魂は何度も蘇る - 著者プロフィール - 中野 京子 (ナカノ キョウコ) (著) 作家、独文学者。北海道生まれ。早稲田大学大学院修士課程修了。著書に『「怖い絵」で人間を読む』『印象派で「近代」を読む』『「絶筆」で人間を読む』『異形のものたち』(NHK出版新書)、『怖い絵』シリーズ(KADOKAWA)、『名画の謎』シリーズ(文藝春秋)、『美貌のひと』(PHP新書)、『西洋絵画のお約束』(中公新書ラクレ)など多数。
-

雪豹の大地 スピティ、冬に生きる | 山本 高樹
¥2,420
雷鳥社 2025年 ソフトカバー 256ページ A5変形判 縦188mm 横148mm 厚さ17mm - 内容紹介 - 巡り巡る命を、見つめ続けた日々。 ヒマラヤの山奥深くに棲まう幻の獣、雪豹。全世界での推定生息数は8000頭に満たず、険しい高山地帯に生息しているため、野生下では目撃することすら困難とされている動物だ。そんな雪豹たちのあるがままの姿を見届けるため、写真家はインド北部のチベット文化圏、スピティに旅立った。 標高4200メートルの極寒の高地。狩る者と狩られる者の命のやりとり。自然の摂理の中で儚い生を生きる、雪豹、狼、狐、アイベックスなどの動物たち。その傍で、大いなる存在への畏れと祈りとともに暮らす人々。ひと冬の間、彼らとともに過ごした日々の中で、写真家が巡り会ったのは……。 『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』で第6回「斎藤茂太賞」を受賞した気鋭の著者による、待望の書き下ろし長編紀行。雪豹や野生動物たちの躍動感のある姿、スピティの祭礼や高地の村の様子など、貴重な写真の数々も収録。 - 目次 - 夏の終わり 雪のない冬 母と子 村での日々 双子の兄妹 雪の到来 狩る者、狩られる者 矢と酒の祭 巡り巡る命 彼らの歌 - 版元から一言 - 雪豹の姿を捉える。その難しさは、様々な書籍や映画などで語られている通り。本書は、『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』で第6回「斎藤茂太賞」を受賞した山本高樹さんが、雪豹に会いに行った旅を記した全編書き下ろしの長編紀行です。 しかし、雪豹を撮影した、という一過性の話にとどまらず、雪豹と他の野生動物や現地に住む人々との関係を深く掘り下げた物語こそが、本書の魅力であり、真価だと思います。臨場感溢れる旅の記録を、ぜひお読みいただけると嬉しいです。 - 著者プロフィール - 山本高樹 (ヤマモトタカキ) (文・写真) 著述家・編集者・写真家。2007年から約1年半の間、インド北部のラダックを中心としたチベット文化圏に長期滞在して取材を敢行。以来、この地域での取材をライフワークとしながら、世界各地を飛び回る日々を送っている。本書のほか、主な著書に『ラダックの風息 空の果てで暮らした日々[新装版]』『ラダック旅遊大全』(雷鳥社)、『インドの奥のヒマラヤへ ラダックを旅した十年間』『旅は旨くて、時々苦い』(産業編集センター)など。『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』(雷鳥社)で第6回「斎藤茂太賞」を受賞。
-

花の辞典 | 新井 光史
¥1,650
雷鳥社 2017年 ハードカバー 282ページ A6変形判 縦120mm - 内容紹介 - 大人気「辞典」シリーズ第5弾! さあ、お気に入りの花を見つけましょう! 五感を通して私たちを癒してくれる花は、生活必需品ではないけれども、日常を豊かにしてくれる大切な存在です。 本書では、春、夏、秋、冬と季節ごとに分類した206種類の花を美しい写真とともに掲載し、 さらにはすべての花に花言葉を添えています。 また、花をより知っていただくために巻末コラムを設け、花の買い方から飾り方、長持ちさせる方法、 簡単な花飾り・アレンジのコツなど幅広く網羅。素敵なイラスト入りなので楽しく学べます。 辞典として読むことはもちろん、ハウツー&ビジュアルブックとしても読み応え十分。 デザイン、そして紙質にもこだわりぬいた一冊です。
-

草の辞典 野の花・道の草 | 森乃おと, ささきみえこ(イラスト)
¥1,650
雷鳥社 2017年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 野や散歩道でよく出会う、「あの」草花の名を知っていますか? 人気の「辞典シリーズ」第四弾! ! 「ハコベ」「ナズナ」「イヌフグリ」「ワレモコウ」……。 本書は、散歩道でよく見かける春夏秋冬の草花193種の美しい写真と、それぞれの花言葉を載せています。第二章では、草や花にまつわる言い回しや季語、名言などを集め、コラムでは「食事の時間」「お茶の時間」「癒しの時間」に分け、可愛いイラストとともに、〝スイバのスープ〟〝シロツメクサ茶〟〝ドクダミ化粧水〟など、野の草花を使った手づくりの料理やお茶、コスメなどのレシピを紹介します。第三章では薬草・毒草をまとめています。知れば知るほど、野の花や道の草が愛おしくなり、温かな気持ちとなれる一冊です。
-

海の辞典 | 中村 卓哉
¥1,650
雷鳥社 2012年 ハードカバー 288ページ 15.2 x 10.2 x 2.6 cm - 内容紹介 - 海にまつわる素敵な言葉を四季折々の美しい海の写真とともに綴る。 目次 1 海の色・音・風 2 波・潮の名前 3 海と海まわりの呼び名 4 海の季節・時間・場所 5 海のたとえ (心・人生 行動・状況・他) 6 海にまつわる大切なことば
-

僕には鳥の言葉がわかる | 鈴木 俊貴
¥1,870
小学館 2025年 ソフトカバー 264ページ 四六判 - 内容紹介 - ようこそ シジュウカラの言葉の世界へ 山極壽一先生(総合地球環境学研究所所長)絶賛! 「類人猿を超える鳥の言語の秘密を探り当てたフィールドワークは 現代のドリトル先生による新しい動物言語学の誕生だ」 :::::::::::::::::::::::: NHK『ダーウィンが来た!』をはじめ国内外のメディアが注目する気鋭の若き動物言語学者による初の単著、ついに刊行! 古代ギリシャ時代から現代に至るまで、言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった。 その「常識」を覆し、「シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っている」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ。 動物学者を志したきっかけ、楽しくも激ヤセした森でのシジュウカラ観察の日々、鳥の言葉を科学的に解明するための実験方法などを、軽快に綴る。 シジュウカラへの情熱と愛情あふれるみずみずしい視点に導かれるうちに、動物たちの豊かな世界への扉が開かれます。読後に世界の見え方が変わる一冊。巻頭口絵にはシジュウカラたちのカラー写真が、巻末にはシジュウカラの言葉を聞ける二次元コードつき。 【編集担当からのおすすめ情報】 本書の草稿を拝読したとき、何より感動したのは、鈴木先生が「シジュウカラのことが好きだ、もっと知りたい」というまっすぐな気持ちで、自然の中に身を置いて根気強く鳥たちをよく観察する姿勢でした。文系、理系、アウトドア派、インドア派問わず、何かを「好き」と思う気持ちを大事にすることで、日常生活の中でも新鮮な驚きや気づきが得られ、ひいては世界的な発見にまで繋がる--これは読者の皆さまにとっても、ポジティブなメッセージとなることと思います。 ちなみに、初の単著となる本文内のイラストはすべて鈴木先生自身によるもの! こまかなところまでかわいらしく描かれているのは、愛と興味をもって丁寧に相手を観察する鈴木先生ならではのタッチです。ぜひお楽しみください。 - 目次 - はじめに 鳥たちの世界へ 小鳥が餌場で鳴く理由 救いと拷問のキャベツ ヒロシ先生の思い出 巣箱をかけた話 都会の住宅事情 繁殖の観察 修士課程の秋と冬 巣箱荒らしの犯人 大発見! ヒナの力 パースの思い出 動物の博士 実家の巣箱 ヒナ救出大作戦 井の中の蛙 シジュウカラに言葉はあるのか? 「ジャージャー」はヘビ! シジュウカラは文を作る ルー語による文法の証明 「ぼく・ドラえもん」実験 翼のジェスチャー カエル人間救出作戦 動物言語学の幕開け おわりに 特別付録 シジュウカラの鳴き声を聞いてみよう 参考文献
-

植物の不思議なちから 古代から語りつがれる72の物語 | ヘマ・マテオス, 山本 朝子(翻訳)
¥2,970
グラフィック社 2024年 ハードカバー 192ページ B5変型判 縦240mm 横170mm - 内容紹介 - 植物は古代より薬効が注目を浴びるとともに、神聖視され、霊的なものと見なされ、医術、魔術、儀式の中心に据えられてきました。 本書では72種の植物を取りあげ、世界各地の伝説や言い伝えなど、さまざまな物語を紹介します。 - 目次 - 不思議な草木、その象徴化 家をまもる/恋に、愛に/悲しみを乗り越える/幸運を招く 薬用植物 心を整える/不安を和らげる - 著者プロフィール - ヘマ・マテオス (ヘマ マテオス) (著/文) バルセロナ大学で哲学と文学を学んだのち、ガーデニング、料理、自然科学など幅広い分野の書籍を執筆。 特に植物と動物に関する幅広い知識を持つ。
-

日本動物民俗誌 | 中村 禎里, 小松 和彦(解説)
¥1,265
講談社 2024年 講談社学術文庫 ソフトカバー 264ページ 文庫判 - 内容紹介 - 山海の神か、田の神か。贄か、神使か、妖怪か――。 サル・キツネ・オオカミ・クマからネコ・トリ・ムシ・サカナまで、日本人は動物たちをいかに認識し、どのような関係を取り結んできたのか。膨大な民俗資料を渉猟し、山/海、家畜/野生、大きさ、人との類似などの基準によってその歴史と構造を明らかに! 25種の動物ごとの章立てで、「事典」的なニーズにも対応。 (解説:小松和彦) 【本書に登場する主な動物たち】 [キツネ]気高き神の使者は、やがて商業神、憑きものへ [イヌ]化け物の正体を見破る特異な辟邪力 [ネズミ]経典荒らしが転じ、仏法の守護者に? [オオカミ]なぜオオカミだけ? 「産見舞い」に赤飯を [ネコ]擬人化の果てに、愛する人の形代に [サカナ]山神はなぜ毒棘持ちのオコゼを愛したのか [ウサギ]ウサギvs.サルvs.カエル「動物餅争い」の結末は? [カニ]甲に浮かぶ悲運の英雄たちの無念 …… - 著者プロフィール - 中村 禎里 (ナカムラ テイリ) (著/文) 1932-2014年。東京生まれ。立正大学名誉教授。専攻は科学史。著書に『日本のルイセンコ論争』『生物学を創った人びと』『危機に立つ科学者』『血液循環の発見』『日本人の動物観』『狸とその世界』『河童の日本史』『狐の日本史』などがある。
-

「絶滅の時代」に抗って 愛しき野獣の守り手たち | ミシェル・ナイハウス(原著), 的場知之(翻訳)
¥4,180
みすず書房 2024年 ハードカバー 368ページ 四六判 - 内容紹介 - 野生動物をどうまなざすか考えることは、わたしたちがどう振る舞うかを考えること。価値ある資源か、御しがたい厄介者か、はたまた守るべき隣人か。異なる価値観に翻弄されつつも、愛しき野獣を守ろうとした者たちの奮闘の歴史が、本書の主題である。 これは、常識変遷のストーリーでもある。ほんの250年前、進化理論は影も形もなく、絶滅の概念さえおぼろげだった。ほんの100年前は、野生動物保護は狩猟のために行うのであって、オオカミやタカなどの捕食動物は駆除すべき害獣だった。そして、世界初の絶滅危惧種保護法が米国で成立したのが約60年前。それ以来、国際的な保護の機運が広がり、いまや「豊かな生物多様性の価値」は常識となりつつある。 このような変化は、科学の発展によるところも大きい。だが、思想を深めた者、法に訴えた者、政治に働きかけた者、そして市民に広くよびかけた者なしには、決してありえなかったはずだ。レイチェル・カーソンやジュリアン・ハクスリー、アルド・レオポルドやウィリアム・ホーナデイなど、挫折や対立をものともせず「行動した者」たちが、今の常識を作ってきた。 自然保護活動には、解決を待つ難題が山積みであり、昔も今も近道はない。先人たちや、今まさに現場にいる人々の奮闘を記した本書が羅針盤となり、これからも続く生物多様性保全の進展を導くだろう。 - 目次 - 序章 イソップのツバメ 第1章 動物を名づけた植物学者 第2章 剥製師とバイソン 第3章 猛女(ヘルキャット)とタカ 第4章 森林管理官と緑の炎 第5章 教授と不死の妙薬 第6章 ワシとツル 第7章 象牙の塔を出た科学者 第8章 サイとコモンズ 第9章 多数を救う少数 終章 ホモ・アンフィビウス 謝辞 人名索引/事項索引/生物名索引/図版出典 - 著者プロフィール - ミシェル・ナイハウス (ミシェルナイハウス) (原著) (Michelle Nijhuis) 1974年生まれ。アメリカの科学ジャーナリスト。専門は保全生物学と気候変動。長年寄稿している『ハイ・カントリー・ニュース』誌ではシリーズConservation Beyond Boundaries(国境を越えた保全)の編集長を務める。また、『アトランティック』誌ではプロジェクト編集者として、Planetのコーナーと、シリーズLife Up Closeのディレクションを担った(2017-2023)。ジャーナリストとしての業績で、AAASカヴリ科学ジャーナリスト賞を二度受賞している(2006、2012)。共編書にThe Science Writers’ Handbook: Everything You Need to Know to Pitch, Publish and Prosper in the Digital Age(2013)、著書にThe Science Writers’ Essay Handbook: How to Craft Compelling True Stories in Any Medium(2016)がある。 的場知之 (マトバトモユキ) (翻訳) (まとば・ともゆき) 翻訳家。東京大学教養学部卒業。同大学院総合文化研究科修士課程修了、同博士課程中退。訳書に、ロソス『生命の歴史は繰り返すのか?――進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む』、ピルチャー『Life Changing――ヒトが生命進化を加速する』(以上、化学同人)、クォメン『生命の〈系統樹〉はからみあう――ゲノムに刻まれたまったく新しい進化史』、ウィリンガム『動物のペニスから学ぶ人生の教訓』(以上、作品社)、ルーベンスタイン『オールコック・ルーベンスタイン 動物行動学 原書11版』(共訳、丸善出版)、王・蘇(編)『進化心理学を学びたいあなたへ――パイオニアからのメッセージ』(共監訳、東京大学出版会)、マカロー『親切の人類史――ヒトはいかにして利他の心を獲得したか』(みすず書房)、マイバーグ『空飛ぶ悪魔に魅せられて――謎の猛禽フォークランドカラカラをめぐる旅』(青土社)など。
-

身体がますます分からなくなる | 小鷹 研理
¥1,980
大和書房 2024年 ソフトカバー 272ページ 四六判 縦188mm 横130mm 厚さ165mm - 内容紹介 - 「からだの錯覚」の研究者が、からだの不確かさや思い通りにいかなさに考えを巡らせる科学人文エッセイ! 知的好奇心を揺さぶる数々のからだの錯覚実験を紹介しつつ、「からだとは何か、脳とは何か」という人文的考察を深めていく。 知らなかった、意識していなかった「自分のからだ」のおもしろさが次々と襲いかかりるエキサイティングな研究と考察。「一冊読めばからだのことがよくわかる」と思っていたら、「なんだかますます分からなくなってきた」という不思議な読後感を味わえます。 - 目次 - ▼第1章 どうしても思い出せない左手のこと 両腕を奪われたディフェンダー 髭にまとわりつくこの左手について 闇に葬られたエイリアンの行動記録 右の頬を打たれたら左の頬を差し出さずにはいられない 外向的な右手と内向的な左手 顔触を奪われることで奪われるもの ▼第2章 誕生日が1日ズレた自分を想像する 奇数が好きですか、偶数が好きですか ブーバとキキの運動学 偶数と奇数を踏みつけてみたならば ブーバ世界のカフェで賑わう4人の女性たち 自己愛をあたりかまわず転写するバースデーナンバー 誕生日をずらすことによるきもちわるさ 奇数が好きになる誕生日、偶数が好きになる誕生日 数字から豊潤な連想世界が広がる女性たち 歴史上、ただの一度しか許されない実験 ▼第3章 20秒間でシャッターを1回だけ押す 生きているものたちのリズム、しなやかなメトロノーム 初めての実験、窮屈に押し込められたシャッターの音塊 好きにボタンを押してください、とはいうけれど 集団を使って緊張を突破しようとする者たち 授業の外に飛び出した集団フリーシャッター実験 集団心理は本当にシャッターチャンスを高めているのか? 自由意志はキリのよい時間に現れる 今日、私は◯◯くんに告白をする ▼第4章 半地下のラバーファミリー錯覚 (第0節 序) 現実と虚構を同一の地平で編み直す (第1節 建築物が「家」になるまで) 身体に宿る家族的なハーモニー (第2節 接合型パラサイトの諸相) 自分と他人の入り混じったもの 出来事の同期体験が「家族」をつくりだす 「におい」という宇宙 他人として出会い直される自分 (第3節 交換型パラサイトの諸相) 身体を収納する「一つ」の容器の潔癖 切断されたラバーファミリー錯覚の憂鬱 (第4節 不可視型パラサイト、そして約束された悲劇へ) ▼終章 ―――会ったことのない同居人(半自己特論) 神経の通っていない自分、としての他人 物語を持たない人間の倫理 未開の皮膚、未開の骨、頻発する「ビッグバン」 デッドライン あとがき - 著者プロフィール - 小鷹研理 (コダカケンリ) (著/文) 名古屋市立大学芸術工学研究科准教授。工学博士。2003年京都大学総合人間学部卒業。京都大学大学院情報学研究科、IAMAS、早稲田大学WABOT-HOUSE研究所を経て、2012年より現職。野島久雄賞(認知科学会)、Best XR Content Award(ACM Siggraph Asia)、世界錯覚コンテスト入賞(2019-2021)など多数受賞。著書『からだの錯覚』(講談社ブルーバックス)
-

ペンギンは歴史にもクチバシをはさむ 増補新版 | 上田 一生
¥3,520
青土社 2024年 ハードカバー 320ページ 四六判 - 内容紹介 - 貴重な図版満載の異色の文化史 氷原の上をよちよち歩くタキシード姿、好奇心いっぱいの「かわいい」やつ。大航海時代から「未知の大陸」のシンボルとしてさまざまな場面で大活躍してきたペンギンには、その一方で食料、燃料などとして利用されてきた受難の歴史もある。現代ではそのたくましさでも脚光を浴びつつあるペンギンから見た、貴重な図版満載の異色の文化史。
-

人類を熱狂させた鳥たち 食欲・収集欲・探究欲の1万2000年 | ティム・バークヘッド, 黒沢令子(翻訳)
¥3,520
築地書館 2023年 ハードカバー 392ページ 四六判 - 内容紹介 - 人類の歴史が始まって以来、 私たちの信仰、科学、芸術、資源の源として存在し続けている鳥類。 精神と生命を支えてきたその生物を、 人はどのように捉え、利用し、そして保護しようとしているのか。 新石器時代の壁画に描かれた208羽の鳥から紀元前の哲学者が「予言者」として扱った鳥、 鷹狩りの歴史、ダ・ヴィンチが興味を引かれたキツツキの舌、 鳥が部位ごとに持つとされた薬効、一夫一妻制の真相、 海鳥の利用と個体数減少、長距離を移動する渡り鳥の研究など、 1万年以上にわたる人間と鳥の関わりを、イギリスを代表する鳥類学者が語り尽くす。 [書評] ティム・バークヘッドは著名な鳥類学者で、優れた科学コミュニケーターでもある。 本書は、1万2000年にわたる鳥類との関わりを、鳥と私たちの視点から描いている。 鳥や鳥好きな人との個人的な出会いを、 巧妙な科学的厳密さを交えて意欲的な歴史研究を通じて、楽しげに語ってくれる。 ――ティム・ディー(作家・ナチュラリスト・BBCラジオプロデューサー) 鳥と人との密接で時として驚くべき関係について一流の鳥類学者がしたためた魅力的な物語である。 ――スティーブン・モス(作家・ナチュラリスト) 古代の時代からの鳥と人の関係を探るこの本は、衝撃的で、刺激と不思議に満ちている。 鳥と暮らす今日の私たちに痛烈な挑戦を投げかけてくれる。 ――イザベラ・トゥリー(『英国貴族、領地を野生に戻す』の著者) 複雑な科学を魅力的で生き生きとしたスタイルで説明する著者の才能は高い評価を得ている。 ――BBC Wildlife - 目次 - 序文 第1章 新石器時代の鳥 鳥類学のゆりかごv 動物壁画の考察 第2章 古代エジプトの鳥 大量のトキのミイラの意味 墓壁に描かれた鳥 古代エジプトで見られた鳥 鳥のミイラの役割 第3章 古代ギリシャ・ローマにおける科学の黎明 生まれる子どもは誰の子か? アリストテレスの方法 自然誌家プリニウス 古代ローマ人の珍味好き 鳥を通して見る世界 第4章 男らしさの追求──鷹狩り バイユー・タペストリー 鷹狩りとステータス 装飾写本と鳥 フリードリヒの『鷹狩りの書』 アリストテレスの復活 鷹狩りに対する逆風 動物に対する敬意 第5章 ルネサンスの思想 キツツキの驚異の舌 解剖学的研究の発展 オオハシの真実を求めて 「有害鳥獣」の指定と駆除 鳥の薬効 第6章 科学の新世界 ターナーの鳥の絵 新しい科学の手法──観察と分類 ドードーの真の姿 魅惑の新大陸 ケツァールの輝き 先住民の鳥利用 ステータスとしての羽 植民地化による知識の搾取 自然科学と宗教のはざまで 第7章 海鳥を食べる暮らし 海鳥の楽園フェロー諸島 フェロー島民による鳥猟 ウミガラスの卵の味 銃がもたらした悲劇 フルマカモメを食べる 人語を真似るワタリガラス セント・キルダ群島の場合 生きるための殺生 第8章 ダーウィンと鳥類学 セルボーンの博物誌とダーウィン 博物誌の読者たち 鳥を飼う利点──鳥の生態と人の思惑 神と自然選択 反ダーウィン論 カッコウという存在の矛盾 ラファエル前派と進化論 ジョン・グールドのハチドリ愛 第9章 殺戮の時代 裕福な青年鳥類コレクター 剥製ブームの到来 世界の大物コレクター 殺生とその正当化 収集活動と絶滅 コレクターの悲哀 収集欲と問われるモラル 博物館の存在意義 収集欲の果てに 第10章 バードウォッチング──生きた鳥を見る 観察して推論する バードウォッチングの発展と標識調査 アマチュア鳥類学者の誕生 鳥好きの分類 鳥類学に向く人とは 鳥を記録する喜び 鳥を追跡する技術 第11章 鳥類研究ブーム──行動、進化と生態学 ある鳥好き夫婦の功績 ドイツの鳥類研究 ティンバーゲンによる動物研究の4つの指標 自然選択が働くのは個か種か 行動生態学の躍進 鳥類学と「利己的な遺伝子」 カササギの配偶者防衛 鳥類理解の深まり 第12章 人類による大量絶滅 消費の末の絶滅 海鳥保護のいきさつ ファッションと羽 鳥類保護の第一歩 ウミガラスと私 ウミガラス研究の魅力 気候変動から受ける影響 長期研究の意義 エピローグ 新時代への転換点 自然への共感 心のときめきと科学 謝辞 訳者あとがき 図版クレジット 参考文献 原註 索引 - 著者プロフィール - ティム・バークヘッド (ティムバークヘッド) (著/文) 世界的に著名な英国の鳥類学者。数々の受賞歴がある。 ロイヤル・ソサエティのメンバーで、シェフィールド大学の動物学名誉教授。 著書に『鳥の卵』(白揚社)、『鳥たちの驚異的な感覚世界』(河出書房新社)などがある。 黒沢令子 (クロサワレイコ) (翻訳) 専門は英語と鳥類生態学。地球環境学博士(北海道大学)。 バードリサーチ研究員の傍ら、翻訳に携わる。 訳書に『フィンチの嘴』(共訳、早川書房)、『鳥の卵』『美の進化』(以上、白揚社)、 『日本人はどのように自然と関わってきたのか』(築地書館)、 『時間軸で探る日本の鳥』(共編著、築地書館)などがある。
-
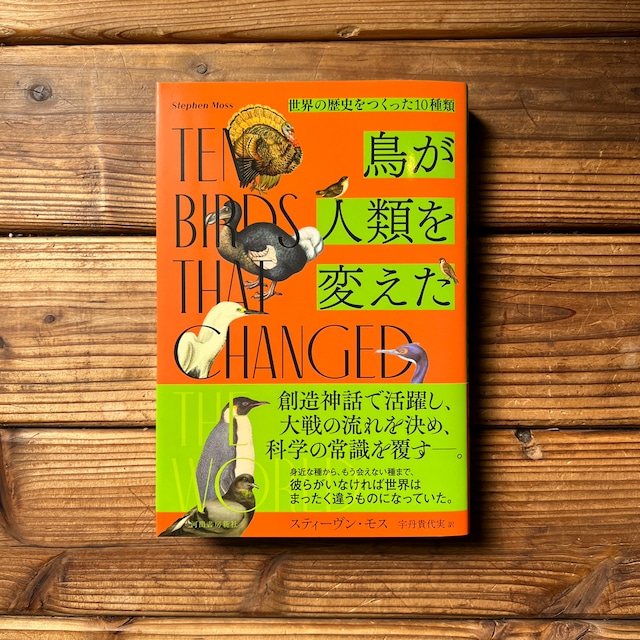
鳥が人類を変えた ――世界の歴史をつくった10種類 | スティーヴン・モス, 宇丹 貴代実(翻訳)
¥3,190
河出書房新社 2024年 ハードカバー 340ページ 四六変型判 縦192mm 横132mm 厚さ24mm - 内容紹介 - 神話に最初に登場する鳥、世界一高価な鳥、大戦の流れを変えた鳥、科学の常識を覆した鳥……。身近な種から絶滅した種まで、世界の見方がまったく変わる鳥たちの物語。 創造神話で活躍し、 大戦の流れを決め、 科学の常識を覆す――。 身近な種から、もう会えない種まで、 彼らがいなければ世界は まったく違うものになっていた。 ●本文より 「わたしが選んだ一〇の鳥はどれも、人類の根元的な要素――神話、情報伝達、食べ物と家庭、絶滅、進化、農業、環境保全、政治活動、権力のおごり、気候非常事態――とかかわりを持つ。これらの要素はすべて、わたしたち人間と鳥との、絶えず変化しながら連綿と続く密接な関係と絡みあっているのだ」 ●原題 TEN BIRDS THAT CHANGED THE WORLD(2023年刊) 【目次】 序 第1章 ワタリガラス 神話に登場する最初の鳥 種としての途方もない繁栄 オーディンの神話 世界創造の象徴でありトリックスター 深遠なる知性 文学とワタリガラスの声 千変万化で複雑な性質 迫害からの復活 ロンドン塔の守護者 第2章 ハト 一万年前からの家畜化 なぜ家畜となったのか 大プリニウスからピカソまで 戦時中の伝令として シェール・アミの物語 第二次大戦の流れを変える ハヤブサ駆除部隊 二一世紀もハトは現役 列車に乗るハト 都市の対ハト全面戦争 青い背景に白い鳥 第3章 シチメンチョウ 北アメリカでの繁栄 先住民との歴史 ヨーロッパへの到来 なぜ“ターキー”と呼ばれるのか 愚かで攻撃的? シチメンチョウは食べるな 野生のシチメンチョウを救え 第4章 ドードー ドードーはわずかな事実しか知られていない いつ姿を消したか、その後何が起こったか ドードーは二度失われた 絶滅のイコン 絶滅の最速記録 危機への反撃 同じ道をたどらずにすんだ鳥たち 今日のドードー 絶滅から何も学んでいない 第5章 ダーウィンフィンチ類 流動的で変化しやすい種 フィンチ神話の起源 ダーウィンの理論を証明する実例 偽りの物語 目の前で生じた進化 進化の実例はフィンチだけではない 分類体系をひっくり返す 欧米の先入観を葬り去る フィンチたちの運命 第6章 グアナイウ 世界一高価な鳥 鳥の糞が生んだ富 グアノと先住民 完璧な解決策 グアノ景気の終わり 中国人労働者の悲惨な境遇 海鳥が直面する脅威 農業の劇的な変化 ほんとうの遺産 第7章 ユキコサギ プルーム狩り マリー・アントワネットとダチョウの羽根 あるハンターの改心 女性グループによる戦い 流行の変化 婦人参政権運動とプルーム貿易反対運動 保護運動の世紀 殉死のあとで 環境保全の成功物語 第8章 ハクトウワシ 北アメリカ最大の猛禽 アメリカの象徴 古代帝国の象徴 神聖ローマ帝国の象徴 第三帝国の象徴 右向きのワシ ワシとドナルド・トランプ 第9章 スズメ スズメ撲滅運動の証人 北京のスズメ虐殺 反対の声をあげた科学者たち 史上最大の人災 傲慢さと無知がもたらした戦い オーストラリアの砂漠での戦い “エミュー大戦争”の敗北 世界全体でスズメが減少している 飢饉は自然災害ではない 自然を征服できるという毛沢東の妄想 同じ悲劇がすでに起きている 第10章 コウテイペンギン 厳冬期の南極で子育てをする 気候変動による“準絶滅” 世界最悪の旅 渡り鳥も気候変動の犠牲者に 留まるべきか、去るべきか 気候危機の影響をうける鳥はほかにもいる 土地利用の変化 よい報せと悪い報せ 謝辞 訳者あとがき 注釈 索引
-

作家とけもの | 野村 麻里
¥2,200
平凡社 2024年 240ページ 四六判 - 内容紹介 - 人と動物の間で重ねられてきた愛憎相半ばする魂の交歓や、剥き出しの命との対決を、作家の視線から物語った随想アンソロジー。
-

キツネを飼いならす 知られざる生物学者と驚くべき家畜化実験の物語 | リー・アラン・ダガトキン, リュドミラ・トルート, 高里ひろ(翻訳)
¥2,640
青土社 2023年 240ページ 四六判 - 内容紹介 - キツネは犬になれるか? シベリアの奥深くに、尾を振り、耳が垂れている、友好的で従順な動物がいる。しかし、外見に反して彼らは犬ではなく、キツネである。これは、何千年もの進化をわずか数十年で再現した史上最も驚くべき繁殖実験の成果だった。本書は科学者たちの驚くべき物語を描くのと同時に、時間を超えて人間と動物を結びつけてきた深い絆を讃える。
-

生きものハイウェイ | 佐々木洋, 中村一般(イラスト)
¥1,760
雷鳥社 2023年 ソフトカバー 208ページ 四六判 - 内容紹介 - 地図にはないけど奥深い、縦横無尽に広がる「生き物の通り道」。 生き物ハイウェイとは、生き物の通り道のこと。この本では、私たちの身近な場所に張り巡らされた「生き物ハイウェイ」を、10のフィールドに分けて紹介します。さらに、そこから焦点をより近づけて、電柱・道路標識・プランターの下・中央分離帯・墓石・朽木の中・ドングリ・郵便受け・セーターなど、それぞれのユニークなハイウェイコースを探します。生き物は、昆虫、爬虫類、鳥、魚、哺乳類など、さまざまなタイプが登場。 著者は、30年以上自然観察を続けてきた佐々木洋さん。その経験を活かして、生き物の通り道はもちろん、特徴・出没ポイント・観察時期・名前の由来なども、豊富な知識と雑学を織り交ぜながらユーモアたっぷりに解説。そこに何かが動いているような気配の漂う、中村一般さんのイラストと合わせて、ぜひお楽しみください。 「この世は、私たち人間だけのものではない。無数とも思える人間以外の生き物も暮らしている。そして、それらの多くは、こちらから遠くまで探しに行かなくても、私たちと、時間と空間を共有しているものなのだ。」(─はじめにより) 目次 1章 住宅街【電線はハクビシンにとっての「けもの道」】 2章 幼稚園の園庭【哺乳類の「登園路」で持ち去られる上履き】 3章 ビル街【自動ドアを通過するSF的ツバメの出現】 4章 寺社の境内【不気味な鳴き声で開幕するムササビのショータイム】 5章 河川敷【地中に広がるモグラのネットワーク】 6章 公園の雑木林【手塚治虫も愛した「オサムシ」の捕まえ方」】 7章 公園の水辺【ヨシの茎に扮する野鳥「ミョウガの妖精」】 8章 大きな道路【世界戦略を企てるトンボのワールドツアー】 9章 大きな橋【辛抱強く待てば見られる「ボラ・ジャンプ」】 10章 番外編 【こんなところに道がある!】 おまけ 執筆中に聞いていた音楽 前書きなど 私は、生き物の通り道のことを「生き物ハイウェイ」と呼んでいる。それは、私たちが生活しているすぐそばに、まるで毛細血管のようにして張り巡らされている。ときには私たちが着るセーターや、郵便受けの中にまで道がある。私たちにとって、そこはハイウェイとは呼べないかもしれない。しかし、生き物にとっては立派な「ハイウェイコース」なのだ。 本書では、私たちが毎日のように目にしている場所に、生き物の通り道がたくさん広がっていることを知ってもらったり、その世界を想像してもらったりすることを最大の目的としている。 「ここに生き物の道があるかもしれないな」と、ぜひ外に意識を向けてみてほしい。バスを待つ10分間、駅の改札口で人を待つ20分間、渋滞中に車内で過ごす30分間などが、きっと愉快なひとときに変わるはずだ。スマートフォンから目を離して空を眺めてみるだけでも、たくさんの発見がある。通勤の途中でも、ショッピングのさなかでも、緑地や歩道などで立ち止まり、意識してまわりを眺めてみると、ここにも、あそこにも、生き物の通り道があるものだ。そして、眺めている間にも、きっと昆虫や野鳥などが通るだろう。 わたしは、自然観察ほど多くの人々が一生続けられる楽しみは、そう多くないと思っている。たとえ仕事に忙殺されていても、歳をとって足腰が弱くなっても、場合によっては病院に入院しても、基本的にはできることなのだ。 「生き物ハイウェイ」の存在を感じることをきっかけに、そして人生の楽しみのひとつに、ぜひ日々の自然観察を加えていただけたら嬉しい。この世は、まさに、ワンダーランドなのだ。 版元から一言 30年以上自然観察者として解説を続け、NHKの『ダーウィンが来た!』や「大河ドラマ生物考証者」としても活躍中の著者が、私たちの身近な場所に張り巡らされた「生き物の通り道」を10のフィールドに分けて紹介します。普段見慣れている景色の中に、生き物の道がたくさんあることを知ると、驚くと同時に外へ向ける意識が変わります。人間にとっては汚い場所の「ゴミ置き場」も、例えばネズミやカラスにとっては大事な道。神社にある「手水舎」や「大木」も、小さな虫やムササビなどの通り道になっているのです。オフィスの窓や壁にだって、道があります。今は、皆スマートフォンを見ながら歩いていることが多い時代。でも、顔をあげて空を眺めてみるだけでも、そこにはたくさんの生きもの達が通っているのです。目線を外に向けて、各場所で一生懸命に生きている生きものたちの世界を知ると、少し優しい気持ちが芽生えるかもしれません。 また、今回イラストは中村一般さん(イラストレーター・漫画家)に、10章分の場所をそれぞれ描いて頂きました。緻密な絵を見ると、思わず生きものの気配を感じます。佐々木さんのユニークな視点とコミカルな文章、そして中村さんの世界観溢れるイラストとともに、「生きものハイウェイ」を是非お楽しみいただければ幸いです。 - 著者プロフィール - 佐々木洋 (ササキヒロシ) (著/文) プロ・ナチュラリスト®️。東京都出身、在住。プロフェッショナルの自然解説者として「自然の大切さやおもしろさを、多くの人々と分かち合い、そのことを通じて自然を守っていきたい」という思いのもと、国内外で自然解説を続けている。30年以上にわたり、40万人以上の人々に、自然解説を行う。著書に『都市動物たちの事件簿』(NTT出版)、『ぼくらは みんな 生きている』(講談社)、『きみのすむまちではっけん! となりの「ミステリー生物」ずかん』(時事通信社)など多数。NHKテレビ『ダーウィンが来た!』など出演。BBC(英国放送協会)動物番組アドバイザー。NHK大河ドラマ生物考証者。 中村一般 (ナカムライッパン) (イラスト) イラストレーター。1995年東京都出身、在住。書籍の装画や漫画の執筆を中心に活動中。イラストレーション青山塾修了。漫画著書に『僕のちっぽけな人生を誰にも渡さないんだ』(シカク出版)、『ゆうれい犬と街散歩』(トゥーヴァージンズ)、作品集に『忘れたくない風景』(玄光社)。現在月刊漫画雑誌「ゲッサン」(小学館)にて『えをかくふたり』連載中。
-

世界を変えた100の化石 新装版|ポール・D・テイラー, アーロン・オデア, 真鍋 真(監修), 的場 知之(翻訳)
¥1,980
エクスナレッジ 2022年 ソフトカバー 352ページ 四六変型判 縦180mm 横128mm 厚さ23mm - 内容紹介 - イギリス・大英自然史博物館で大人気を博した展覧会が 書籍になって日本上陸! 新たな情報と化石の和名表記を加た <よりわかりやすい新装版> 始祖鳥やティラノサウルスなど誰もが知る生物の化石だけでなく 光合成の痕跡、恐竜の卵、サメの糞、火山灰に埋もれた足跡など当時の状況を語る化石も網羅。 まだ知らなかった化石に出会える、至極の一冊。 地質年表、一部復元図付き。 目次 【掲載化石一例】 第1章:先カンブリア時代 [エイペックス・チャート] 最古の化石は生物か? [ストロマトライト] 大酸化事変が生んだ生命体 [中国・陡山沱の化石] 謎に満ちた胚etc. 第2章:古生代 [アノマロカリス] カンブリア爆発で生まれた「奇妙なエビ」 [ハルキゲニア] 陸に上がり、生き延びたムシ [キンクタン] 初期の棘皮動物 [オルソケラス] オルドビス紀の捕食者の王 [ウミユリとプラティセラス類] 2億年続いた共生関係 [プテリゴトゥス] 巨大かつ獰猛な古代サソリ [クックソニア] 地上を征服した植物 [ケファラスピス] あごのない魚 [コムラ] 天敵を避ける棘とげだらけの三葉虫 [レピドデンドロン] 森が生んだ燃料 [ヘリコプリオン] 渦を巻く歯は、進化も奇抜? [ディメトロドン] セックスアピールか、ソーラーパネルか? [ウミツボミ] 史上最大の大量絶滅 etc. 第3章:中生代 [三畳紀の微小巻貝] 小さいことはいいこと? [キノドン類] 爬虫類から哺乳類へ [メガゾストロドン] 大物のデビューは前途多難 [ムカシトカゲ] 安住の地で今も生息 [グリファエア] 泥に埋まって生きた「悪魔の足の爪」 [プロミクロケラス] 大量死したアンモナイト [首長竜] ネッシーは実在したか? [ネオソレノポラ] 色を残した藻類 [始祖鳥] 鳥類の誕生 [トンボ] 巨大化した昆虫たち [ランフォリンクス] 最初の空飛ぶ脊椎動物、翼竜 [イグアノドン] 「恐竜」と名付けられた生物の歯 [クモ] 琥珀の中のクモと糸と獲物 [アラウカリア] 進化の天才? モンキーパズルの大木 [孔子鳥] 性選択で美しく進化した鳥 [白亜層のカイメン] 微粒子を濾し取る海底ポンプ [ティロキダリス] 軍拡競争の歩みが見えるウニの棘 [トロオドンの巣] 高度な子育ての痕跡 [エドモントサウルス] 極地の冬も生き延びた恐竜 [初期のプラントオパール] 恐竜が食したイネ科植物 [ティラノサウルス・レックス] 伝説の王 [ベレムナイト] K/Pg境界の大量絶滅 [有孔虫] 小さく単純なサバイバー etc. 第4章:新生代 [サメの歯] 化石の由来を示す「癒しの石」 [オニコニクテリス] 空に進出した哺乳類 [オフィオコルディケプス] ゾンビと化したアリの咬み跡 [貨幣石] ピラミッドに残る単細胞生物 [トロフォン] ダーウィンの巻貝 [バシロサウルス] 「トカゲの王」はクジラだった [ゴキブリ] 琥珀の中の止まった時間 [エジプトピテクス] 霊長類の起源 [チャネヤ] 花を咲かせる植物の誕生 [メトララブドトス] 断続平衡論を支持する外肛動物 [プロコンスル] 類人猿に近いか、ヒトに近いか [ディスコグロッスス] 独特の姿に進化したカエル [サメのコプロライト] 螺旋型の糞の化石 [サカマキエゾボラ] 圧倒的に少ない左巻きの貝 [巨大ウォンバット] アボリジニに伝わる怪物_バニップ [グリプトドン] アメリカ大陸間大交差も生き延びた哺乳類 [ラエトリの足跡] 350万年前の灰のなかの3人 [メノルカの小型ヤギ] 島嶼矮小化で生き延びた動物 [ステップマンモス] ヒトと共存したマンモス [ジャイアントモア] 植物に生きた証を遺した鳥 [アクロポラ・ケルヴィコルニス] 絶滅寸前のシカツノサンゴ [ステラーカイギュウ] 虐殺された海の巨獣 [ホモ・ハイデルベルゲンシス] 私たちにいちばん近い祖先? etc.
-
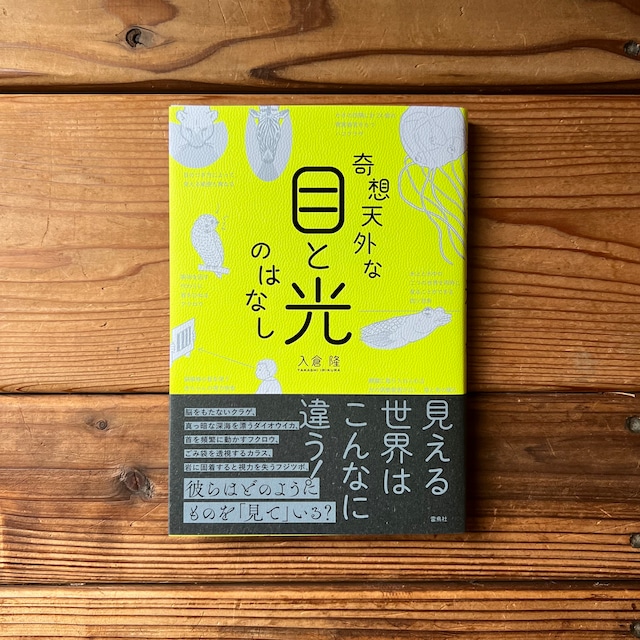
奇想天外な目と光のはなし | 入倉 隆
¥1,980
雷鳥社 2022年 ソフトカバー 216ページ 四六判 - 内容紹介 - 見える世界はこんなに違う! 脳をもたないクラゲ、真っ暗な深海を漂うダイオウイカ、 首を頻繁に動かすフクロウ、ごみ袋を透視するカラス、 岩に固着すると視力を失うフジツボ、彼らはどのようにものを「見て」いる――? 心理学、光学、工学の横断領域にあたる「視覚心理学」を研究する著者が、 光や色の特性、目の仕組み、さらには世界中の動物たちの目の構造や特性についても調べ、 「これは面白い!」と思った話題を掻き集めた、知的好奇心をくすぐる一冊。 ダーウィンを困らせた「目の進化」から、動物たちの「見る・見られる」の攻防戦、 蛍光色や輪郭線が目立って見える「視覚の不思議」まで、“目から鱗”のトピックが凝縮。 ・どうして目は「頭部」に「2つ」ついているの? ・動きの速い動物ほど視力が良い? ・真っ暗な深海に棲む動物にも目があるのはなぜ? ・話せない赤ちゃんの視力検査はどうやるの? ・昼間に強い光を浴びないと夜に冷えやすい? ・人間よりも色覚の多い動物は、より鮮やかな世界を見ている? ・バイオレットライトは目を良くする? ブルーライトは目を悪くする? 生物進化論、視覚心理学、光学をまたいで、 目と光が織りなす奇想天外な世界を旅してみませんか? 目次 まえがき chapter1:進化 01「目」の誕生と進化 02 複眼と単眼で捉える世界 03 複雑なカメラ眼の成り立ち 04 陸上の目、水中の目 05 さまざまな機能をもった動物の目 chapter2:見る・見られる 01 どうして目は頭についているの? 02 どうして目は二つあるの? 03 コミュニケーションに長けた人間の目 04 視野を広げるための工夫 05 動きの速い動物ほど視力が良い? 06 動きの遅い動物の目は退化する? 07 わずかな色の差を見分ける目の仕組み 08 動いているものは目立って見える chapter3:見えない世界 01 紫外線を捉える動物たち 02 人間も紫外線を感じている? 03 赤外線を使って見えないものを見る 04 偏光パターンで太陽の位置を知る 05 光を追うもの、避けるもの 06 発光しておびき寄せる 07 真っ暗な深海に棲む動物にも目がある理由 08 電気を使って捕食する chapter4:どこまで見える? 01 人の視力はどこまで発達するの? 02 見ている世界にだんだん慣れていく 03 どのくらい遠くまで感じられる? 04 どのくらいの速さで感じられる? 05 光の量を調節する瞳孔の形 06 何色まで見分けることができる? 07 見えない色、感じない色 chapter5:感じる光 01 光を色として感じる仕組み 02 構造が作り出す複雑な色 03 光環境に適応する目の仕組み 04 太陽の光が生活リズムを作る 05 光の色や強さで体感温度が変わる 06 光の方向で眩しさが変わる 07 高齢になると光はどのように感じられる? 08 光は目を良くする? 悪くする? 09 色によって変化する味覚 10 目を閉じたら、感じ方はどう変わる? あとがき 参考・引用文献 前書きなど 動物学者でもない私が、なぜ動物たちが見ている視覚世界や目の仕組みについての本を書いたか、疑問に思うことでしょう。私は大学の電気工学科で、光の見え方や感じ方を扱う「視覚心理学」の研究を行う一研究者です。 大学卒業後は、東京の三鷹にある国立研究所で航空灯火について研究をしていました。航空灯火とは、滑走路に設置されている灯火のこと。飛行機に乗ると滑走路で点灯している光を見たことがありますよね、あれです。 夜間や霧でもパイロットが迷うことなく滑走路を見つけて着陸し、真っ直ぐに走行できるのは、灯火が照らし出す経路を目印にしているからです。上空から航空灯火がしっかり見えるかどうかは、多くの人命がかかっているパイロットにとっては最重要事項の一つなので、私たち研究者が明るさは適切か、上空から見て眩しさを感じないかなどを調べて、現場で生かしているのです。 これが縁となり、大学に移ってからは、心理学、光学、工学の横断領域にあたる視覚心理学の研究をするようになりました。 視覚心理学の研究では、不思議なことがたくさん発見されています。一例を挙げると、床や机の上ではなく壁を照らすと、いつもより部屋が広く感じられます。こうした光が与える心理的な効果を探求するうちに、視覚心理学の基礎となる光や色の特性、目の仕組みについても詳しく調べるようになりました。さらには人間の目だけでなく、世界中の動物たちの目の構造や特性についても興味が湧いていったのです。 人は見た目からかなり多くの情報を読み取っています。黄色く熟したバナナがたわわに実っている様子を見たら、「甘くて美味しそう」と思うでしょう。房が緑色だったら、「まだあまり甘くはなさそうだな」と判断して、熟すまで待つはずです。房が茶色っぽく変色していたら、「もう傷んでしまって食べられないかも」と、食べるのを諦めるかもしれません。 人間の目がバナナの色を識別できるのは、ごく当たり前のことのようですが、実はかなり発達した目をもっていないとできないことです。特に人間ほど高度な色彩感覚をもつ動物は、哺乳類でもそれほど多くはありません。 例えば、身近なペットである犬や猫は、色を識別する視細胞の種類が人間よりも少ないため、赤色を見分けることが困難です。血液の色を「赤色」と認識できるのは、哺乳類では霊長類だけだといわれています。 一方、一部の動物たちには、人間の目には見えない光や色が見えています。例えば、花の蜜を吸うモンシロチョウなどの昆虫は「紫外線」を感知することができるため、紫外線を反射する花びらは、きっと人間よりも目立って見えているでしょう。このように、動物のほとんどが、私たちとは異なる世界の中で生きているのです。 さらに、光そのものが私たちの身体に大きな影響を与えることも分かっています。例えば、日中、薄暗い場所で過ごすと、明るい場所で過ごした場合と比べて、夜に寒さを感じやすくなるそうです。よく赤や黄色を「暖色」、青色を「寒色」と呼んだりしますが、実際に光の色や強さによって体感温度が変化する研究結果も報告されています。 本書は、こうした光や目にまつわる不思議でアッと驚く話を紹介しながら、普段、何気なく見ている世界を新しい角度で眺めてもらえたらという思いで書きました。具体的には次のような構成になっています。 chapter1「目の進化」では、簡単な光を感じるだけの器官からどのようにして複雑な目へと進化したのかについて語ります。chapter2「見る・見られる」では、動物の目が捕食者か被食者、動く速度などによりその構造や機能がどのように異なるのか、chapter3「見えない世界」では、太陽光を利用しながら巧みに生き抜く生き物について紹介します。chapter4「どこまで見える?」では、赤ちゃんが成長に合わせて目の機能をどのように発達させていくのか、動物がどこまで色を識別できるのかなどについて、chapter5「感じる光」では、色の見え方や感じ方、光が視覚以外に及ぼす影響について見ていきます。 とにかく私自身が、「これは面白い」と思った話題をたくさん集めてみました。ぜひ、私と一緒に目の不思議な世界を探検してみませんか。 版元から一言 地球に棲む生き物の多くは太陽光の下で暮らしています。光を利用した生物の生存戦略は多岐に渡り、その中の一つに「目」という感覚器官の発達が挙げられます。「目」の作りによって、感知することのできる「光」も違い、また目のつく位置や視力、色覚の違いでも「見える世界」は大きく異なります。紫外線を捉える鳥やチョウ、赤外線を感じるヘビが見ている世界は人間には想像ができません。さらに同じ人間でも、人種によって虹彩の色が違うことで「眩しさ」の感じ方が異なることや、まだ視力が発達していない赤ちゃんや、青色と黒色の区別がつきにくい高齢者が見ている景色も同じではないと考えられます。 この本を通して私たちがふだん「当たり前」に思っている視覚の不思議を再発見するきっかけになればと思います。また「視覚心理学」「光学」を専門にする著者の眼差しによって、目の進化や仕組みの話を「生物学」だけに留めることなく、様々な角度から眺められるようになっている点も見どころです。実際のカバーは普通の黄色ではなく、蛍光黄色を使っているので、鮮やかな発色で目を引きます。 - 著者プロフィール - 入倉 隆 (イリクラ タカシ) (著/文) 芝浦工業大学教授。1956年(昭和31年)香川県生まれ。1979年早稲田大学理工学部電気工学科卒業。運輸省交通安全公害研究所などを経て、2004年より現職。博士(工学)。元照明学会副会長。専門は、視覚心理、照明環境。主な著書に、『脳にきく色 身体にきく色』(日本経済新聞出版社)、『視覚と照明』(裳華房)、『照明ハンドブック 第3版』(オーム社)などがある。
-

絶滅へむかう鳥たち 絡まり合う生命と喪失の物語 | トム・ヴァン・ドゥーレン, 西尾義人(翻訳)
¥2,640
青土社 2023年 ハードカバー 288ページ 四六判 - 内容紹介 - 一つの種が絶滅するとはどういうことか。ダナ・ハラウェイ氏、マーク・ベコフ氏推薦。 絶滅とはある特定の種の最後の一個体が死ぬことを意味するのではない。絶滅はそのはるか前からなだらかに、しかし着実にはじまっているのだ。絶滅の過程にいる種と人間はいかなる関係が結べるのか。消えゆく種に配慮するとはどういうことか。絶滅の過程で人間が負いうる義務とは何か。すでに多くのことが語られてきた絶滅をめぐる問題を、絶滅にむかう五種の鳥たちの生から問い直す。解説・近藤祉秋





